地方創生推進交付金とは?要綱・スケジュール・事例紹介
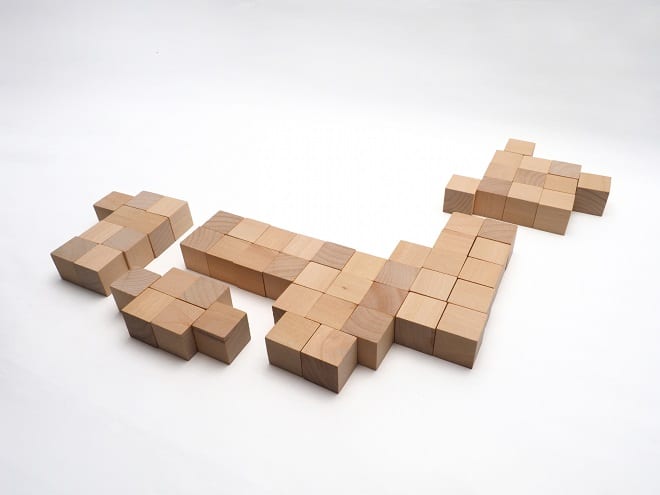
目次
はじめに

少子高齢化に歯止めがかからず、人口の減少は当初の予測よりもさらに急激に進んでいます。
首都圏や大都市圏に暮らしているとなかなか実感できませんが、地方には存続が危ぶまれる900もの自治体があると言われています。
こうした状況に危機感を持ち、2014年の第2次安倍内閣発足時以降、「まち・ひと・しごと創生」事業が開始されています。
その一環として地方の公共団体に支給されるのが、「地方創生推進交付金」です。
かつての「バラマキ型交付金」とは異なり「地方創生推進交付金」では、確かな地方創生戦略が求められます。
実施されている事業に対しては、検証と軌道修正を重ねながらの予算をかけた分の効果と持続性を要求し、最終的には地方の経済の自立を促すものです。
各地域が地元の活性化に苦心する中、国を挙げて地方創生に取り組むための足がかりとなるお金です。
この交付金についての活用状況は地方によっても異なりますが、すでに将来に期待ができる効果を上げている例も数多く見られます。
地方創生推進交付金とは

①地方創生推進交付金の概要
地方創生推進交付金は地方公共団体を対象として、交付されるものです。
これを申請するためには地域再生計画を作成し、その内容が内閣総理大臣の認定を受けるに値する事業として認められる必要があります。
地方の総合戦略に基づいた地方が主体となった地域再生事業であることが条件で、そのほかにも継続性をもち数年にわたる事業であるといった要件が示されています。
②地方創生推進交付金の事業タイプは3つ
地方創生推進交付金の事業タイプには、以下の3つがあります。
- 先駆タイプ… 官民協働、地域間連携、政策間連携などの新しい試みや斬新なアイデアが含まれている事業
- 横展開タイプ… 先駆的・優良事例の掘り下げ・拡大・浸透を図る事業
- 隘路打開タイプ… 既存事業の困難な点を発見し、打開する事業
まったく新しい事業を開始する場合には先駆タイプ、さらにその事業を拡充し、地域に浸透させる事業が横展開タイプとなります。
地方創生推進交付金の歴史がまだ浅いため、主にこの2つのタイプのいずれかで申請がなされることが多くなっています。
③地方創生推進交付金の目的
地方創生推進交付金の目的は、単に事業資金を地方に投げかけることではありません。
地方主導の事業を支援することによって、地域の稼ぐ力を向上させるところにあります。
地方創生推進交付金では、KPIの設定やPDCAサイクルの構築が要となります。
これらの手法を組み込み、また既存組織のような縦割りからの脱却を図ることで、効率的かつ堅固な事業の骨組みを作り上げます。
地域再生法に基づく法律補助の交付金により、安定的な制度・運用を確保し、地方の事業推進を安心して行える環境を提供するのが本施策の意図です。
最終的には事業運営が円滑に成されるようになり、安定した収益が上げられることで、各自治体の事業が自走できるのを目指します。
交付金の手を離れた地方経済が、独り立ちして未来に向かって着実に歩み出すのを期待しています。
④想定される事業イメージ
- 先駆性のある取組及び先駆的・優良事例の横展開
民間と行政の枠組みを超え、また地域間が交流や協働をしながら、実施していくことが求められます。
施策同士が連携することで、さらに相乗効果が起こり、地域創生の大きな波となることが期待されています。
事業の推進役となる各地域における主体組織が形成され、中核となる人材が選出また育成されることで、強力なリーダーシップが誕生します。
具体的な事業の例としては、地域観光の振興や、地域商社の発足、生涯活躍が可能な街づくり、子どもたちの農山漁村体験プロジェクト、地域ぐるみの働き方改革推進、商店街活性化の実施などが挙げられます。
- わくわく地方生活実現政策パッケージ(移住・起業・就業支援)
首都圏、大都市圏からのUIJターンの促進と、地方における労働力の確保についての先進的な対策が期待されています。
事業の例としては地場の中小企業への就業を促進する事業や、地域課題の解決につながる事業の起業、女性や高齢者など潜在する労働力を掘り起こすための就業支援などが挙げられます。
地方創生推進交付金要綱

①交付金額
31年度の交付上限額はタイプ別に以下のようになっています。
<先駆タイプ>
・事業期間:5年度以内
・交付上限額(事業費ベース):都道府県6億円、中枢中核市5億円、市区町村4億円
<横展開タイプ>
・事業期間:3年度以内
・交付上限額(事業費ベース):都道府県2億円、中枢中核市1.7億円、市区町村1.4億円
<隘路打開タイプ>
・事業期間:3年以内
・交付上限額:(事業費ベース)1億円
交付金は事業費の1/2とされ、残りの地方負担金については地方財政措置が講じられます。
地方創生推進交付金の申請についての要件としては、以下のようなものがあります。
<先駆タイプ>
具体的な評価基準(KPI)を設定し、PDCAサイクルにより、事業の効果検証、見直しを行うこと。
上記については、適時公表する必要があります。
さらに、以下の4つの要素を満たしていなければなりません。
- 自立性
- 官民協働
- 地域間連携
- 政策間連携
また事業推進主体の形成、地域社会を担う人材の育成・確保についても審査の観点に加味されます。
これらの要件については、外部有識者を交えて厳正に審査が行われます。
<横展開タイプ><隘路打開タイプ>
具体的な評価基準(KPI)を設定し、PDCAサイクルにより、事業の効果検証、見直しを行うこと。
上記については、適時公表する必要があります。
さらに「自立性」と他3つの要素のうち、いずれか2つの要素を満たす必要があります。
これら2つのタイプについても、「先駆タイプ」と同じく事業推進主体の形成や地域社会を担う人材の育成・確保が審査の要点として加味されます。
③地方創生推進交付金スケジュール
地方創生推進交付金の初年度スケジュールは、プランの策定、交付申請、関係各府省の参画を得ながらの審査、交付、事業の実施という流れとなります。
次年度以降は検証・KPIの達成状況の報告がなされた後、必要に応じて地方版総合戦略の見直しが行われます。
その後再検証の上、次年度以降の交付に反映されるという流れです。
具体的な日付は年度によって多少異なりますが、およそ以下のようなスケジュールで進められます。
- 4月募集開始
- 6月上旬申請受付
- 8月上旬採択事業の公表
- 8月下旬交付決定
地方創生推進交付金活用事例

事例①岡山県美作市
美作市の「美作市の魅力発信プロジェクト」に対する採択額は、3,017,000円でした。
つながりの深いベトナムをメインターゲットとするインバウンド戦略として、観光と外国人移住に力を入れています。
ユニークな取り組みとしては、ベトナム人材をまちづくりコーディネーターに採用し、同市に対する外部的な視点からの魅力向上と掘り起こしを進めています。
加えて特産品の海外への販路拡大へも取り組み、人材不足解消と農作物のブランド化推進という大きな柱を据えて地方再生にまい進しています。
事例②北海道小清水町
北海道小清水町の「農+観+福で紡ぐ“稼ぐ力”向上プロジェクト」に対する採択金は、32,28,000円と決定されました。
同町は以前より農業の担い手を確保するための取り組みを進めていましたが、雪による農閑期の長期化が新規参入の不安材料となっていました。
そこで実施したのが、温泉熱を利用したハウス整備です。
さらに観光農園での農業体験ツアーなどを企画し、農繁期・農閑期のしごと創出に乗り出しました。
加えて「農福連携」の考えにより、障がい者の就労支援のための支援事業所を設置。
就労訓練や受け入れ農家とのマッチングを実施しています。
農業・観光・福祉の3分野をリンクさせた独自の施策を展開し、注目を集めています。
事例③宮崎県椎葉村
宮崎県椎葉村の「秘境の未来を変えるイノベーション拠点施設整備計画」の採択額は、357,419,000円となっています。
日本三大秘境のひとつと称される椎葉村は、九州山地の中央部に位置しています。
四方を国定公園の山々に囲まれ、狩猟、焼畑などの民俗文化と平家伝説が残る地です。
人口は約2,700人と小規模ですが、国指定重要無形文化財の神楽といった地域資源を有します。
この山奥の村が富士ゼロックスや宮崎電子機器などの企業と連携し、IT拠点づくりを進めています。
ファブラボ・テレワークセンターを開設し、地域資源を活用した商品開発やIT人材育成を行う施設としてだけではなく、WEB会議スペース、さらに住民の交流ラウンジとしての機能も付帯させています。
仕事の創出と継続的な運営により、Iターン・Uターンを促す仕組みづくりを推進。
同施設には村外からの利用者向けに宿泊機能も提供しており、施策の見学や企業の研修施設、学生の合宿施設などへの活用が可能です。
仕事と地域の暮らし、そして人の交流。すべてを総合的に拡大させ、イノベーションを起こす取り組みが見られます。
まとめ

地方創生推進交付金は、地方主体で継続可能な事業を実施していくためのブースター的な役割を担う交付金です。
過去のようにただ国が資金提供を行うのではなく、地方の行く末に確実な効果をもたらすための公的な投資と言えるでしょう。
申請にあたってはKPIの設定とPDCAサイクルにより、客観性をもった事業運営を行う計画が求められます。
地方創生は、一時的にお金を与えられたからと言って簡単に成せるものではありません。
各地域から急激に人が消えているという厳しい現状の中、地方創生を実現するためには、縦割り意識を捨て、官民・地域内外の力を結集させることが重要です。
地域に生きる人が強い危機感と再生への意識をもち、地方創生推進交付金をテコにして未来へ続く道を切り開いていかなければなりません。











